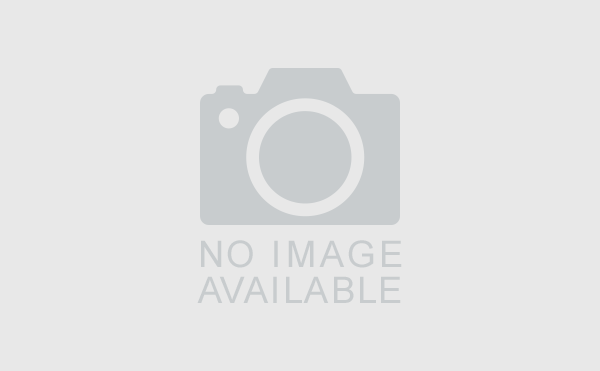1.概要
日時:2025年7月19日(土)14時~16時 会場:オンライン 参加者数:17名
2.内容
1)自己紹介・世話人選出
2)個人研究報告
①西村 光太郎(順天堂大学大学院)
「体育授業における教師と運動中の児童の相互行為分析」
②村下 慣一(立命館大学大学院)
「スポーツ社会学におけるヴェーバー的アプローチの批判的超克に向けた予備的考察
:マックス・ヴェーバーの『宗教社会学』を導きの糸として」
3. 報告
2025年7月19日、オンラインにて2025年度第1回学生フォーラムを開催した。当日は、本学会研究委員の先生方を含め17名が参加した。
まず、参加者の自己紹介、および次期学生フォーラム世話人の選出を行なった。新世話人には、一橋大学大学院の小杉亮太、早稲田大学大学院の舩木豪太、立教大学大学院の藤杏子と八木一弥が選出された。
大学院生からの個人研究報告のセッションでは順天堂大学大学院の西村光太郎氏、立命館大学大学院の村下慣一氏の2名から報告をいただいた。
西村氏の報告は、実際の学校現場(特に本研究では小学校)における、体育実技の授業展開の困難さに着目したものであった。体育の実技は、他の教科に比べて具体的な指導法が確立されづらいことから、現場における参与観察を通した質的な調査が重要だとして、児童が運動している際に先生がどのような行動(指導)をしているかを分析、検討し、そこで何が起こっているかを明らかにしようとした。その後、フロアからの質問では、特に安全性や規律に関わる教員の指導(帽子を被ること、ボールを安全な場所に置くこと)における生徒の反応を中心に議論がなされ、小学校における体育の〈場〉特有の構造へと議論が派生していった。また、指導の際、教員が頻繁に発する「ちゃんと」という言葉の意味の解釈についても多様に含意があることが推察され、その点の分析についても新たな可能性が開かれるものであった。
また、村下氏の報告は、マックス・ヴェーバーの宗教社会学と、それをラディカルに再解釈したブルデューの「宗教〈界〉の構造」モデルに焦点を当てながら、スポーツ社会学における現代的古典である『儀礼から記録へ』を「批判的超克」の対象として取りあげ、グットマン批判を展開したものであった。質疑応答のセッションにおいては、報告内容にとどまらず、歴史研究における理論援用の可能性やその手法へと議論が展開された。議論の一つとして、歴史研究に社会学理論を援用していく際、理論のルーツによって説明できる事象やそうでないものもあり、その点についていかに乗り越えていくのかというものがあった。西洋社会をモデルとして分析し、構築された理論を、日本や東アジアの事例などにおいて応用することに関して、大学院生全体で新たな気づきや学びを得るものであった。
文責:学生フォーラム世話人(小杉、船木、藤、八木)